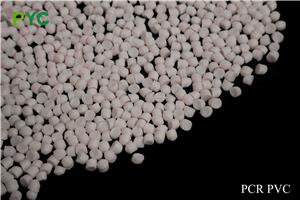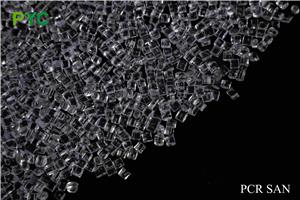生分解性プラスチックとリサイクルプラスチック
生分解性プラスチックとリサイクルプラスチックは現在、持続可能な開発の分野で注目されている話題であり、その実現可能性について、材料の物理的特性、製造プロセス、経済的および環境的実現可能性の側面から詳細に議論されます。
I. 材料の物理的特性の実現可能性
生分解性プラスチックとリサイクルプラスチックは、従来のプラスチック材料を代替するために、物理的特性に関して一定の要件を満たす必要があります。生分解性プラスチックは通常、強度、靭性、透明性など、従来のプラスチックと同様の物理的特性を有しています。材料の組成と構造を調整することで、所望の物理的特性を実現できます。リサイクルプラスチックは回収・リサイクルプロセスを経て得られるため、従来のプラスチックとは物理的特性が異なる場合があります。しかし、適切な技術と処理方法を用いることで、リサイクルプラスチックが特定の用途における物理的特性の要件を満たすようにすることが可能です。
II. 生産プロセスの実現可能性
生分解性プラスチックの生産プロセスは比較的成熟しており、従来のプラスチック製造設備を用いて生産できるため、導入・普及は比較的容易です。再生プラスチックの生産プロセスには、廃プラスチックの収集、選別、粉砕、洗浄、再生といった工程を含む回収・リサイクルプロセスが含まれます。これらのプロセスには追加の設備やプロセスが必要となる場合もありますが、技術の発展に伴い、再生プラスチックの生産プロセスは改善・最適化され、より実現可能かつ効率的なものとなっています。
3. 経済的実現可能性
生分解性プラスチックおよびリサイクルプラスチックの経済的実現可能性には、多くの課題と機会が存在します。生分解性プラスチックは、主に原材料の選択と製造プロセスの制約により、通常コストが高くなります。しかし、持続可能性への需要が高まるにつれて、生分解性プラスチックの大規模生産によってコストが低下することが期待されています。リサイクルプラスチックの経済的実現可能性は、プラスチックの回収とリサイクルのプロセスに左右されます。効率的なリサイクルシステムと高度な再生技術が確立されれば、リサイクルプラスチックのコストは従来のプラスチックと競争力を持つ可能性があります。さらに、政府の政策支援と市場促進も、分解性プラスチックおよびリサイクルプラスチックの経済的実現可能性を高める可能性があります。
IV. 環境面での実現可能性
生分解性プラスチックとリサイクルプラスチックは、環境面での実現可能性において大きな利点を有しています。まず、生分解性プラスチックは自然環境で分解されるため、環境への影響を軽減できます。生分解または物理的分解によって小さな分子に分解され、最終的には微生物や自然プロセスによって代謝されます。これにより、土壌や水域におけるプラスチック廃棄物の蓄積が軽減され、野生生物や生態系への潜在的な悪影響も軽減されます。
第二に、再生プラスチックの使用は、バージンオイルなどの再生不可能な資源への依存を効果的に低減することができます。廃プラスチックをリサイクル・再生することで、新たなプラスチックの生産量を削減し、有限資源の消費量を削減することができます。また、再生プラスチックの使用は、埋立処分や焼却処分の必要性を低減し、これらの廃棄方法に伴う環境問題を軽減することにもつながります。
さらに、生分解性プラスチックやリサイクルプラスチックの使用は、温室効果ガスの排出を削減することができます。従来のプラスチックの製造工程では、大量の化石燃料を燃焼させ、二酸化炭素などの温室効果ガスを排出します。一方、生分解性プラスチックやリサイクルプラスチックの製造工程では、主に廃プラスチックや再生可能資源を原料とするため、温室効果ガスの排出を削減することができます。
総じて、分解性プラスチックおよびリサイクルプラスチックの実現可能性は、物理的特性、生産プロセス、経済性、環境保護の観点から、一定の課題と機会を提示しています。技術の進歩と社会の意識の高まりに伴い、持続可能なプラスチックへの需要は高まり、分解性プラスチックおよびリサイクルプラスチックの開発と応用をさらに推進するでしょう。同時に、政府、企業、消費者の協力と支援も、分解性プラスチックおよびリサイクルプラスチックの実現可能性を実現する上で重要な要素です。
河南平源新材料テクノロジー株式会社について
河南平源新材料科技有限公司は、環境技術革新に注力し、持続可能なリサイクルプラスチックソリューションの開発と普及に尽力する企業です。先進技術と革新的な思考に基づき、廃棄プラスチック資源を高性能材料へと変換し、プラスチック産業の持続可能な発展に積極的に貢献することに尽力しています。
I. 会社概要
河南平源新材料科技有限公司は2017年に設立され、河南省富溝県経済開発区に工場を構え、再生プラスチックの研究開発、リサイクル、生産、販売を一体化した先進的な再製造企業です。浙江省寧波市と広東省東莞市にそれぞれ営業センターと倉庫拠点を構え、世界有数の再生プラスチックリサイクルソリューションプロバイダーです。現在、15の国と地域、50社以上の外資系企業、800社以上の工場企業にサービスを提供しています。
深刻化する地球規模の気候問題は人類共通の課題であり、持続可能な開発は人類共通の福祉です。
2020年9月、習近平国家主席は第75回国連総会の一般討論演説で、2030年までに炭素ピーク、2060年までに炭素中立を達成するという中国の野心的な戦略目標を厳粛に発表した。
当社は長年にわたり、人類が深刻化する環境問題の解決に尽力し、再生プラスチックの潜在的価値を深く探求し、人類の生活環境の継続的な改善を推進してきました。近年、当社は再生プラスチック分野をリードし、ESG実践を先導し、グリーンで低炭素な生産とライフスタイルを積極的に推進し、より大きな価値を継続的に創造しています。
同社は2020年から2022年にかけて、それぞれ年間3万4000トン、4万7000トン、3万5000トン、合計11万6000トンの再生プラスチックを処分する予定だ。
第二に、同社の科学的研究と認証資格
当社は国家級ハイテク企業であり、河南省の特殊目的企業であり、河南省周口市再生プラスチックリサイクル工程技術研究センターである。
当社は、第22回中国国際投資貿易博覧会および2022年中国国際グリーンイノベーションテクノロジー博覧会におけるグリーン開発優秀企業に選ばれました。
当社は、GRSグローバルリサイクル基準認証を取得しました(国内リサイクルプラスチック活用企業として初)。
UL 出塁率 2809認証(リサイクルプラスチックの使用に関してこの認証を取得した世界で6番目の企業)
ISO9001品質システム、14001環境システム、45001労働安全衛生管理機関の認証。
当社は、米国食品医薬品局 FDA のテストレポート、ドイツ新食品栄養製品法 LFGB のテストレポート、フランス国際検査局 BV のテストレポートなど、国際的な第三者によるテストレポートを取得しています。
第三に、同社の研究所建設
当社は、国内リサイクルプラスチック業界で唯一の高水準パイロット実験室を構築し、専門的な研究開発チームを擁し、中国科学院プロセス工学研究所、中国科学院化学研究所、中国科学院大連化学物理研究所、鄭州大学、河南理工大学、大連理工大学などの研究機関や大学と緊密に協力しています。
主な試験機器は、落球試験機、デジタル表示カンチレバービーム衝撃試験機(ISO規格およびASTM米国規格)、分光光ボックス、分光色差計、温湿度計、メルトフローレート計、高精度電子天秤、直読電子密度計、ゴム硬度計、サーボ万能材料試験機、タッチスクリーン材料水平および垂直燃焼試験機、ツインスクリュー高混合可塑化パイロットラインです。
第四に、同社の主力製品と顧客
同社のeコマースネットワークの構築と推進、そしてブランド構築の恩恵を受け、RABS、RPP、RPET、RPA、RRE、RPPなどのリサイクルプラスチック製品は、主に日用品、日用化学品、衣料、靴・帽子、電子・電気、自動車、石油化学などの業界で使用されています。主な顧客は、LGケミカル、暁星、錦湖、博羅化学、LGケミカル、BASF、レゴ、デカトロン、シャネル、エスティローダーなど、国際ブランドや世界トップ500企業です。
V. 会社の今後の発展計画
当社は10年間の将来を見据えた事業計画を経て、廃プラスチックのリサイクルから高付加価値リサイクル製品の応用に至るまで、産業チェーン全体の高度化を実現しました。標準化、グループ化、産業化という発展理念を堅持し、自主的な知的財産権とリサイクルブランドの構築に注力し、技術とブランドのアウトプットを通じて業界全体の高度化を推進します。持続可能な発展に向けたグリーン、低炭素、技術主導の循環型経済産業システムの構築に全力を尽くし、ESG(環境・社会・ガバナンス)の実践と高い水準での社会的責任の遂行に努め、グリーン、低炭素発展の模範となる企業を目指します。
今後40年間、再生プラスチック産業は爆発的な発展を遂げ、1兆ドル規模の再生プラスチック市場需要を形成するでしょう。当社は、産業チェーンの上流と下流の企業、第三者機関、公益団体、政府と積極的に協力し、新たな発展段階に基づき、新たな発展理念を完全かつ正確に全面的に実施し、新たな発展パターンを構築し、再生環境保護材料の利用率の向上、資源利用効率の向上、リサイクル産業チェーンの拡大、生態文明の構築の促進、グローバルな再生環境保護戦略目標の達成に貢献することを目指して、再生環境保護材料の利用率の向上、資源利用効率の向上、リサイクル産業チェーンの拡大、生態文明の構築の促進を目指しています。